【赤玉土】 有機質を含まない深層火山灰性の赤土。
水はけ、通気性が良く、鉢植え用に腐葉土等と混ぜて使用します。
【一年草】 タネをまいて一年以内に開花結実して枯れる草花の事。
【一季咲き】 一年に一回、一定の時期に開花する性質の事。
ほかに四季咲き等があります。
【園芸品種】 品種改良によって人為的に作り出された植物。
「園芸種」とも言います。
【雄蕊(ゆうずい)】被子植物の花を構成する要素の一つで、花粉を入れる袋状の
葯と葯を支える花糸という部分で構成されます。
一般的には「おしべ」といわれますが、雄ずいとも呼ばれます。
おしべの種類には、一本ずつ離れたものや合生したものがあり、
二強雄ずい、四強雄ずい、単体雄ずい、二体雄ずい、三体雄ずい、集葯雄ずい等があります。
【開花球】 植えれば確実に開花する球根。
【花芽】 芽には、葉になる「葉芽」と花になる「花芽」があり、
通常花芽は葉芽より大きい。
花芽ができる事を「花芽分化」といい、
花芽分化の時期は種類によって異なります。
読み方は「はなめ」とも読みます。
【隔年開花】 1年おきに花が咲く事。
ある年に花が咲きすぎると翌年は花芽を付ける力が無くなる為。
【花序】 花軸上の花の並び方。
花の集まり自身を言うときもあります。
【花床】 頭花の小花を付ける部分。
または花柄の先端の花葉をを付ける部分。
「花托」とも言います。
【花柱】 めしべの注頭と子房の間の部分。
【株立ち】 根本から数本の幹が伸びている樹木や草花の形。
【株分け】 大きくなった株から子株を分けて植える事。
根詰まり予防、株の老化防止と増殖が目的の場合もあります。
【花柄】 花序の花を付ける小枝。
【花弁】 花びら。
集まって花冠を構成すること。
【果胞】 雌ずいを包む袋状の器官の事。
果実になっても残る。
「果嚢」とも言います。
【花葉】 生殖の為に変形して花を構成する葉の事。
がく、花弁。
【緩効性肥料】効き目が緩やかで、長い間持続する肥料の事。
【桐生砂】 鉄分の多い黄褐色の山砂。
粒子が大きく多孔質で、通気性、保水性が良い。
【管挿し】 葉芽のついた茎の中間を切り取って行う挿し木の事。
【互生】 同じ種類の中にみられる違い。
大きさの大小、花色や形の違い等の事。
【根茎】 地中を横にはってねの様に見える茎。
【雌ずい】 めしべの事。めしべと同じ「雌蕊」と書く。
【宿根草】 地上部が枯れても地下部が残り、
毎年新しく芽を出し生長する草花。
【上弁】 スミレ属の花の5枚の花弁の内、上側の左右1枚の花弁の事を言います。
【穂状花序】 無限花序の一種で、総状花序を作っているそれぞれの花が柄を失って、
花が直接花軸についた花序の事。
【総状花序】 下から上へ、あるいは周りから中心部へ咲いてゆく無限花序の一つ。
柄のある小花が長い円錐形、または円柱形に並び、
下から咲いていくものの事。
穂状花序との違いは花に花柄がある事です。
【総包】 キク科の頭花、セリ科の散形花序等に、花序の軸が極端に短縮して、
包葉が花序の基部に密集したもの全体の事を言います。
1枚ずつの包葉を総包片と言います。
【速効性肥料】 効き目が速く表れる肥料。
化学肥料の多くがこれに当たります。
【側根】 主根から分かれて出る枝根の事。
【対生】 葉が向かい合って出るつき方。
【堆肥】 易分解性有機物が微生物によって完全に分解されて肥料の事。
有機肥料と同義語で用いられる場合もあります。
【多年草】 1年で枯れてしまう1年草に対し、多年にわたって生長する草花。
【断根】 根を切り詰める事。
【短枝】 樹木の間にある節と節の間(節間)が短いものを短枝といい、長いのを長枝といいます。
開花して果実をつける枝(結果枝)は短い程結実が良い。
【追肥】 元肥に対して、植物が育ち始めてから与える肥料の事。
速効性の液肥を使う事が多く、追い肥とも言います。
【接ぎ木】 増やしたい枝や芽を切り取り、別の株の枝や茎につ接いで活着させる事。
【摘心】 枝分かれをさせたり、生長をそろえる為に茎の先端部を摘み取る事。
【頭花】 複数の花が集まって、まるで一つの花の様に見えるもの。
【筒状花】 キク科、マツムシソウ科等に見られる合弁花。
一つの花の全花弁がり筒状となる事。
筒状花のみ、または舌状花とともに頭花を作ります。
【頭状花序】 花軸が茎の先端で皿状に幅広く広がり、柄のないいくつもの花が
密生してつく型式の花序の事。
【胚】 受精した卵細胞が発育し、種子の中で休眠している幼体の事。
【胚軸】 胚の一部で、胚の中軸となる円柱形の部分。上端に子葉と幼芽を、下端に幼根をつけます。
【胚珠】 子房の中につくられ、受精発達して種子となるもの。
【杯状花序】 トウダイグサ科の花に見られる様な、杯形の花序の事をいいます。
【胚乳】 受精した極核が発育してできた種子の中の組織で、胚が生育する為の養分になります。
【副花冠】 花冠の中にできる花冠状の付属物。
【覆瓦状】 うろこ等が重りあっているときき、一方の端が順次、次のものの植えになり、
瓦を伏せた様に重なっている状態の事。
【覆土】 タネを撒いた後、その上に土をかける事。通常、タネの大きさの2~3倍の厚さで行います。
【富士砂】 富士山の火山灰土を園芸用に加工したもの。通気性や保水性が良く、
ランや山野草栽培に用いられます。
【腐食質】 土壌中の動植物の死骸が、微生物によって分解されて出来た有機化合物などの有機物の総称。
【浮遊植物】 ウキクサなどの、根が水底に固着する事なく、植物全体が水面に浮いて生育する植物。
【浮葉植物】 ヒツジグサなどの、根は水底の地中にあり、葉だけ水面に浮かぶ植物。
【腐葉土】 落ち葉が積もって腐ったもの。有機質に富み、他の土と混ぜて鉢植え用などに用いります。
【閉果】 種子が熟しても果皮が裂けない果実の事。果皮が裂ければ裂果といいます。
【閉鎖花】 開花せず、つぼみの中で自花受粉して結実する花の事。スミレ属やホトケノザ等にみられます。
【胞果】 裂果のうち、果皮が薄く不規則に裂けた1種子のもの。
【包葉】 花の下にある変形した葉の事。包ともいいます。
【保護剤】 枝を切った時、殺菌と乾燥防止の為に、切り口に塗る薬剤の事。
【匍匐】 地表を這うこと。
【匍匐茎】 地表を長く伸びて這う茎の事。節から根と葉を出して、子苗を作ります。
走出枝(ランナー)とも呼ばれます。
【実生】 植物を種から育てる事で、一度にたくさんの苗が作れます。
【密閉挿し】 挿し木の際に、根がない挿し穂から水分の蒸散を防ぐ為に、ガラス板やビニール等で
開口部を覆って高湿度を保つ方法。鉢植え毎にビニール袋に入れたりもします。
【無限花序】 花序の主軸に花がつく事がなく、主軸は理論上、無限に生長を続け、
花は側枝につく花序で、花は下から咲き上がります。
【雌蕊(しずい)】 花粉がつく柱頭、中に胚珠を持った子房と、それをつなぐ花柱などからなる、
花の雌性生殖器官の事で、受粉して実となり種子となります。
雄蕊と同じ様に対義語で雌蕊といわれる事もありますが、
一般的には「めしべ」と呼びます。
【元肥】 植物を植えたり種を撒くときに、最初から土に施しておく肥料の事。
【葯】 花粉を作る袋で、花糸と共におしべの一部をなします。花糸のつき方によって、低着葯、側着葯、丁子着葯
等があり、やくの裂け方によって、縦裂葯、横裂葯、孔開葯、弁開葯などと呼びます。
【葯核】 葯と葯の間に入り込んだ花糸の一部。
【誘引】 園芸栽培の際に、茎やつるを支柱や紐になどに結び付けて形を定める事。
【有限花序】 花序の軸の先端に花がつき、軸はそれ以上伸びる事ができない。
次々に出る側枝もその先端に花がつきます。
【雄ずい】 おしべの事。おしべと同じく「雄蕊」と書きます。
【癒合剤】 幹や枝を切った時に癒合組織を発達させる作用がある薬剤の事。
癒合とは:剪定等の切り口や傷口がふさがったり治ったりする事。
【葉腋】 葉の付け根のすぐ上の部分のこと。
【葉耳】 イネ科等の葉身の根元の葉舌の両側から耳状に突き出た一対の突出物の事。
【葉序】 葉の茎へのつき方の事。
【葉鞘】 葉の下半分がさやになって茎を包む部分で、単子葉植物に普通にみられます。
主にイネ科やカヤツリグサ科によく発達しています。
【葉状枝】 葉が緑色でへん平な葉の幼な形になり、葉に代わって光合成を行うもの。
【呼び接ぎ】 根がついたままの木同士で接ぎ木をする方法です。
または、枝を付けたい位置まで接ぐ枝を曲げて接ぐ事。
【葉舌】 イネ科の葉身と茎を包む葉鞘の境に出来る薄い膜状の突出物の事。
種によって形、大きさが異なり、ときに一列に並んだ毛となっています。
【葉脈】 葉身に通る管束の事。その走り方によって網状脈、平行脈に大別します。
【翼弁】 ちょう形花冠の5枚の花弁の内、上位の左右一対の花弁の事。
【呼び接ぎ】 根が付いたままの木同士で接ぎ木をする方法。
または、枝をつけたい位置まで接ぐ枝を曲げて接ぐ事。
【裸花】 花被がまったくない花の事。
【竜骨】 りん片、かく片、葉しょう等が長軸方向に折れ曲がって鋭い稜となったなったもの。
イネ科植物の内類によくみられます。
【鱗茎】 地下部にある茎のまわりを、養分を蓄えた無葉緑の葉(りん片)が密に取り囲んだもの。
ユリやタマネギ等にみられます。
【輪生】 茎の1節から3枚以上の葉の出る葉のつき方の事。
【鱗葉】 小さな鱗の様な形をした葉の事。ヒノキやサワラコノテガシワ等のヒノキ科に多い。
【裂果】 裂開花ともいいます。乾果の一つで閉果の対語。熟して乾くと避ける果実の事で、袋果(カガイモ)、
豆果(マメ科)、さく果(アサガオ)、蓋果(オオバコ)、胞果(カヤツリグサ)等があります。
【連作障害】 同一地に同じ植物をつくり続けると生育が悪くなる事。「忌地」ともいいます。
【ロゼット】 根元から出た多くの葉が地表に放射状に広がったもの。互生葉の節間が極端に短縮してできています。
【ロックガーデン】 岩石を配した間に高山植物等の植物を植えて楽しむ庭の事を総じていいます。
【矮性】 基本種に比べて著しく草丈が低い事。

・グロボーサ-263x180.jpg)
-e1609146000818.jpg)





-640x396.jpg)

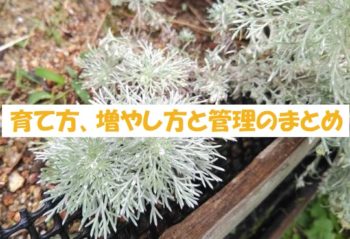

-640x396.jpg)
